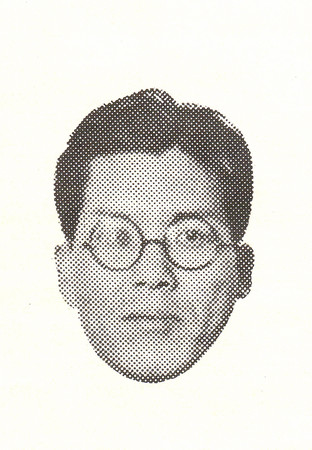一 赤堤
「恭次郎君は、カラカラと日和下駄の音をさせてやってきた。世田谷、赤堤一丁目の山本というお百姓さんの畑の中にあった私たちの家へ。つまり図書出版渓文社へ、昭和六年の秋のある昼過ぎであった。彼は風呂敷包みから『断片』の原稿を出して〈是非これを作ってもらいたい。表紙にはボルトのカットをつけてくれ給え。ぼくの希望はそれだけで、あとは君にまかせるから、たのむ。〉と言って、その夜は泊まった。…脊椎カリエスで寝ていた竹内てるよ君も寝床に、はらばいになったまま仲間にはいり、賑やかな晩餐となった。恭次郎君はよく笑い、しゃべり、きげんがよかった。竹内君もよく笑う。」 神谷暢〈詩集『断片』が出来るまで〉
赤堤、詩人の竹内てるよが詩集を刊行していた図書出版、渓文社の所在地であった。そして一九三〇年代から十数年間の住まいでもあった。
渓文社は何処に在ったのか……刊行された書物のこと、いつ迄続いたのか……渓文社、これ迄に赤堤に存在した唯一の出版社である。
渓文社に関する詩人たちの記述は少なく竹内てるよを調べ始めた当初、渓文社は遥かに遠い存在であった。当時の住所は刊行書の奥付や同時代の出版物の広告に記されているので、それを手がかりに現在のおおまかな地域は調べられる。一九三七年刊行の「一万分の一地形図〈経堂〉」を調べ、地形図に見入る。経堂と豪徳寺駅間の北側には畑地が広がっている。その畑地の中に住居の印が点在している。道は農道であるのか畑に沿って湾曲している。三一年の萩原恭次郎は、数年前に開通したばかりの小田急線を利用し、豪徳寺駅か経堂駅から降りたのであろうか、或いは世田谷線の最寄駅を利用したのか。
恭次郎はしばらく若林に住んでいたので世田谷にはなじんでいた。若林に居た当時、豪徳寺の境内までは散歩の範囲であったことは推測できる。さらに甲州街道方面まで足を伸ばしたことはあるのだろうか。
背が高い日和下駄の恭次郎は七〇年前の赤堤を歩き竹内たちの住まいに向かっていた。恭次郎を待つ二人は貧しいゆえ特別なもてなしは用意できなかったが歓待の気持ちだけは充分にあった。
渓文社の出版活動の情報は限られていたが少しずつ文献が集まってきた。主宰していた二人は共に詩人。神谷暢は七七年に死去、著作は刊行されていない。もう一人、竹内てるよは自伝も含め著作は多いが、この時期に関しての記述はあえて曖昧にしているのか赤堤にいた時期は具体的には書かれていない。竹内は長命で二〇〇一年に九六歳で死去。
渓文社の時代、二人と近かった詩人たちの著作を調べるしかなかった。八八年に亡くなっている詩人秋山清が著書『あるアナキズムの系譜』(七三年発行)で章をたて渓文社の事蹟を述べていた。またそのテキスト中には神谷暢との対談も短いが収載されていた。
それによると渓文社は短い期間であるが竹内以外にも後に評価され著名になる詩人たちの詩集の出版に力を注いでいた。
文献をさらにたどると六八年に発行された『萩原恭次郎全詩集』(思潮社刊)に付された小冊子に神谷が当時の思い出を掲載していた。そのテキストの一部が冒頭に引用したものである。
赤堤の渓文社の一室。むしろ木造の貸家の住まいそのままを出版業務も兼ねた部屋という方が正しいかもしれない。
竹内は赤堤の家を回想、以前はここはまだ竹藪や畑ばかりであり農家は二、三しかなく、子供にあめを一つ買ってやるのも、畠を越えて歩いて行った、しかし電車が開通してから、あまり歩かなくなった、と語る。渓文社の一角は世田谷でもあまりひらけないところであったが竹内たちがこの家に住むようになってから、大分にひらけて来たというのである。借家建てとしては一番古い家で、東京のお金持ちが、病身のむすこのために建てたので狭い、と住まいの由来と様子も語っている。(『愛と孤独と』、五二年発行、宝文館刊)。
恭次郎は渓文社の二人を前にして、自分の詩集を刊行する目途がついたせいか酒なしの晩餐でも気分がよかったようである。恭次郎はおとなしくなっていた。ほんの一〇年程前、『赤と黒』の刊行前後、本郷白山の南天堂二階で連日酒を飲んで騒いでいた「疾風怒涛」時代の恭次郎とは異なっていた。そして「活動」の時期も経て、故郷での家族との生活が恭次郎を変えていた。
昭和の始めの世田谷である、畑地の周りは竹やぶがあり樹木も多かったであろう。部屋で半日談笑していると鳥たちの啄みの声も恭次郎たちに心地よく響いたであろう。竹内にとってこの数年間は充実した日々であった。神谷の詩人としての同志的な生活の支援に始まり、草野心平による初めての詩集『叛く』の刊行、六郷での坂本七郎の励まし、各詩誌への精力的な発表。竹内にとって恭次郎の消息は詩誌を通じて承知していても直接会う機会はそうあるものではなかった。話は弾んだに違いない、詩論や仲間たちの消息、直接聞くことができるということは竹内に活力を与えただろう。そして恭次郎の二冊めの詩集を刊行する作業に立ち会えることは大きな喜びであった。
恭次郎に限らず二人と関わりがあった詩人たちの貧乏ではあるが熱い思いの時代を探り、渓文社と書物をめぐる物語の序章としたい。
二 萩原恭次郎
一九三一年まで、詩集『死刑宣告』が恭次郎にとっては唯一の著作であった。話題をよんだが、ダダイストや未来派の芸術家との共同作品の側面もあり、恭次郎にとっては表現し終えた作品集であり再版以降は増刷を承諾しなかった。
そしてアナキズムの立場を強めた恭次郎にとって仲間たちの手で自分の詩集が制作されることはその数年の活動を集約したものになり刊行するという決意は強いものであった。
恭次郎は一八八九年五月二三日、群馬県南橘村に生れる。二三年一月、壺井繁治、岡本潤らと雑誌『赤と黒』を創刊、『赤と黒』は、当時のダダイズム、未来派などの文学運動の先駆となる。二四年頃連日のように本郷、白山上の南天堂レストランに出入り乱酔していた。二五年、第一詩集『死刑宣告』を長隆舎より出版、二七年一月、雑誌『文芸解放』を壺井繁治、小野十三郎、岡本潤らと創刊。同年五月、世田谷町若林に移る。八月、文芸解放社はサッコ、ヴァンゼッティ釈放要求運動の中心となり、恭次郎も八月二三日に築地小劇場で抗議演説、その後米国大使館に押しかけ石川三四郎、新居格らと共に検束留置される。
これまでの恭次郎の年譜では以下の回想には触れられていない。当時の詩人仲間、金井新作は「まだ、世田谷の若林で、我々が共同生活をしていた頃、或る日、恭次郎と共に尾崎喜八を訪ねた」と回想している。またこの年、駒場に住んでいた詩人の秋山清がたびたび往来していたことは秋山自身の回想にある。「彼(恭次郎)が東京世田谷の若林あたりの、まわりに水田の多かった家に住んでいた頃で、そこからそう遠くない駒場にいた私は休みの日など時々出かけていったそのころ小野十三郎は私とは帝大農学部を距てた代々木富ヶ谷に住んでいた」『あるアナキズムの系譜』。徒歩で二〇分もかからない距離であろう。そうすると記述としては残されていないが小野も恭次郎と往来していた可能性は充分ある。小野は南天堂出入りの時期、そして文芸解放社で恭次郎と行動を共にし一番親密な時期であった。若林の具体的な番地を現時点では確認することができない。恭次郎は頻繁に書信を出すことはなかった。とくにこの時期の便りは警察との緊張関係も影響し受けたほうもすぐに処分をしていたのではないか。ただ『黒色青年』(黒色青年連盟機関紙)一二号(一九二七年九月発行)の消息欄に「文芸解放社は東京市外世田谷若林五二七壺井方に移転」とある。恭次郎が壺井と同下宿か近所に間借りしていた可能性は大きい。
少し金井に触れる。一九〇四年、静岡県沼津町生まれ。詩に関心をもち二六年、尾崎喜八を知る。二七年『文芸解放』、他にもアナキズム文芸誌の同人となり寄稿も多数。慶大仏文科を卒業、三四年には古本屋を経営しつつ自らの詩集を刊行する。同志の詩人碧静江と結婚。
恭次郎は二八年一〇月頃、東京を離れる。二九年五月、前橋で草野心平が刊行していた詩誌『学校』第五号に「断片」と題した詩を三編寄稿する。以降同じ『断片』という題で詩を発表し続ける。三一年、詩集出版を相談するため上京、「詩神」社を訪問。小野十三郎らと交遊。翌日高橋新吉、坂本七郎、渓文社の神谷暢、竹内てるよを順次訪問。さらに既述の渓文社訪問となる。一〇月にその第二詩集『断片』を出版。三二年、謄写刷りの詩誌『クロポトキンにおける芸術の研究』を謄写刷りで発行、自分で原紙をきり刷る。
恭次郎は仲間達との共同性を意識していた。一九三一年一月に発表された評論、〈生産本位の芸術より消費本位の芸術生産へ〉において展開している。恭次郎は、詩をつくるつくらん、製本する製本せん、そんな問題は更に重要さを持たないと主張。…作者も共同者も助言者も、植字工も製本工も、各自の能力に従って共同の思想、全体に尊重の出来る作品なり行動なりをつくり出す以外の何者でないと、共同作業の過程が重要だと訴えている。恭次郎は文化人として、作家としての詩人の位置にとどまる気はさらさもなかった。仲間たちとの共同を求め、それぞれが担当する部分で力を発揮することが最良の作品をつくりあげると確信していた。竹内の苦闘も表現している。
詩〈あんまり考えるな──ある女の像──〉抄
肉体は木乃伊になろうと最後の呼吸まで正しく吐いて死体にならう。かつてその乳房は乳児の歯のない口が噛んだのだ。/……新宿の雑踏の片隅で赤や白の花を売る。それはごみごみの屋根裏から貧血の足を踏んで出て来たのだ。/ ……この日、彼女を肩にしてその屋根裏に夜を明かして介抱してくれた青年の顔は、火の如く燃えていた。 /……怖ろしい喀血の咽喉に湿布する手。カリエスの痛みに気絶する彼女を縛して堪へさせる手。
竹内の二八年頃の生活を描写。病気の身体で新宿駅頭に立つ竹内の存在は仲間の詩人たちの間ではすでに知れわたり、その竹内の生存をかけた花売りの姿を恭次郎は表現している。青年は神谷であろうか看病の姿を描いている。
三 竹内てるよ
竹内は詩作を始めるまで、その短い人生において大きな苦難を経験してきた。一九五二年に発行された自伝『いのちの限り』(竹内てるよ作品集一、宝文館刊)を参考にする。一九〇四年、竹内は札幌で生誕後から生母と生き別れる。父親は銀行員、母親は半玉であり二人の仲は許されなかった。父親は借金を作り家には寄り付かず判事として北海道を異動する祖父と祖母のもとで育てられる。祖父の退職後一家で東京に出るが竹内は家計を支えるため、女学校を中退し商事会社の事務員となる。文学好きで仕事を終えると創作にいそしんでいたという。一六歳で『婦人公論』の短編募集に応募し入選、それが縁で他の出版社を紹介され記者となる。二四年五月、二〇歳で結婚、出産。二四歳にて脊椎カリエスに罹り病床に伏し離縁され、子供は手放してしまう。そして闘病生活の過程で詩の創作を始める。二八年『詩神』(福田正夫編集、実務は神谷暢)に作品を持ち込む。小田急線代々木上原駅近くに住まいがあったという。病身で我が子と引離され貧困の中で詩の執筆を続けるという生活に根ざした女性の登場は詩人仲間に衝撃を与え同情が広まった。二九年はアナキズム系文芸誌にも寄稿が始まる。「当時竹内君の病状は悪く、ほとんど毎日の喀血、血便、貧血による 人事不省状態の連続」と神谷は回想している。〈『渓文社』事始め〉。この頃の竹内の詩は晩年の著作にも収録されることもあるが、「評論」は初出誌でしか読むことができない。掲載誌は『黒色戦線』二九年四月号(第一巻第二号)である。
〈或る婦人参政権論者への手紙〉「Kさん 婦人参政権ははたしてそれを得ることによって全日本のしひたげられた女達の希望と幸福とをかち得るほど、それほど重大なものでせうか? Kさん おしつけがましい社会運動にはどん底生活者の婦人達はすべて愛想をつかしました。…参政権よりも一升の米です。…Kさん …私は現制度の破壊と、新しきアナキズムの社会の建設とを主張したいと思ひます……」
次に、『黒色戦線』五月号(第一巻第三号)では「生みの母」へ呼びかける形で、自己の出産、公娼廃止運動への批判を語る。この自己の出生に関しては戦後の回想、エッセイで繰り返し触れられて行くが活字化されたのは『黒色戦線』誌が最初ではないのか。
〈母さんあなたは生きていますか〉「母さんあなたは生きていますか。それとも、もう死んでしまはれたでせうか。…私は、こゝであなたへの積年の思慕や、感傷に沈んでゐるべきでないことをようく知ってゐます。」とまず生き別れといわれている母親への呼びかけで文章を始めている。
「母さん、…売れっ子であったあなたの妊娠は、烈しい鞭となってあなたを責め店の女将のけはしい言葉や、同輩たちの冷酷なさゝやきの中にどんなに心せまい思ひをなさったでせう。……」
後年、竹内が聞かされたわずかな母親の出産前後の置かれた状況を述べている。
「母さん、現在東京のブルジョア婦人達は、彼女達のおざなり婦人運動の中に公娼廃止といふのもやってゐます。……私の身内に流れるあなたの血は、はっきりとそれを笑ってゐます。……この社会の苦悩から私達を解放するのは、決して少数政治家や支配者の寛容ではありません。民衆の中に民衆の生んだ正義への革命の日をおいて何時を信ずることが出来るでせう。……」
この結論は当時の仲間たちと話し合い、運動紙誌を読み、急速にアナキズムを学ぼうとした影響が強く出始めている。気張った言い方ではあるが竹内なりの自分の境遇と重ねた精一杯の表現である。竹内は前述したように、坂本七郎の個人詩誌『第二』にも詩を掲載。仲間たちの詩誌へ毎月寄稿する。
病身で自ら生活費を稼ぐという生きる欲求のエネルギーは周りの詩人たちを動かして行く。男の詩人たちも貧困の中で詩作を続けてきている故中途な同情ではないだろう。子と離され生活と表現を続ける竹内の存在に圧倒されていたのだろう。三〇年には秋山らの『弾道』、三二年には恭次郎の『クロポトキンを中心にした芸術の研究』に寄稿。同誌には「草野心平君、ヤキトリ屋……」「坂本七郎君、失業中」「竹内てる代君、病気依然重し、気でもっている、『第二曙の手紙』出す」「神谷暢君、無政府主義文献出版年報出版(発禁)」と恭次郎が仲間たちの動向を簡単に記している。北海道、山形の『北緯五十度』、福島の『冬の土』誌と列島を縦断し竹内の寄稿先は広がってゆく。
- カテゴリ: